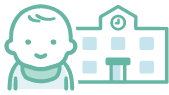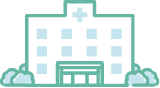雪国の暮らし方
本文
小千谷市は全域が特別豪雪地帯に指定されており、市街地、山間地ともに冬季は雪に覆われます。
雪国ならではの苦労もありますが、ウインタースポーツや雪景色、雪上イベントなど、雪国でしか味わえない楽しさもあります。
また、道路や公共施設は、除雪体制や消雪設備などが整備され日常生活への支障はほとんどありません。
積雪について
例年、11月下旬~12月初旬に初雪が降り、12月下旬から3月頃までが積雪期間となります。この積雪を地元では根雪(ねゆき)と呼び、12月下旬から2月上旬まで降雪日が多くなります。2月下旬頃から降雪日が徐々に減り、4月頃雪解けを迎えます。
積雪量は市街地で1~2メートル程度、山間部では3メートルを超えることもあります。

道路の雪対策
消雪パイプ
「消雪パイプ」と呼ばれる融雪装置が多くの道路に設置されています。消雪パイプは、地下水をポンプでくみ上げ、道路に埋め込んだパイプを通じて路面のノズルから道路に散水して、雪を溶かします。
かつては、除雪をするにも雪のやり場がなく、うずたかく積もった雪が通行に支障をきたしていましたが、消雪パイプのおかげで冬でも夏場と変わらない路面状況が確保されるようになりました。
降雪時の車の運転の心強い味方です。

除雪車
消雪パイプのない道路は、降雪後、降雪深10センチを超えると除雪車が出動します。出勤や通学時に支障とならないよう早朝に作業が行われ、日中に道幅を広げる作業が行われます。
また、除雪した雪は道路脇に積み上げるため、道幅が広く設計されています。山間部では積み上げた雪の壁の高さが5メートルを超えることもあります。


家庭の雪対策
私道や道路から玄関、車庫までの私有地は個人で除雪を行います。昔は「かんじき」で雪を踏み固めて歩けるようにする「道踏み」を行っていましたが、現在は、スコップやスノーダンプで雪を除いたり、小型除雪機が主流となっています。
市街地などは除いた雪を側溝に流すことのできる「流雪溝」が整備されているところもあります。


雪下ろし(家屋の除雪)
積雪が増えると屋根の除雪(雪下ろし)が必要になります。雪下ろしはスコップやスノーダンプを使って行いますが、近年は、雪下ろし作業の軽減のため、建て方や屋根の形状を工夫した住宅が増えています。
代表的な克雪住宅方式は以下の3種類です。
耐雪式
柱の部材等を強固にし、2~3メートルの積雪に耐えられるように設計された住宅です。大雪などで基準以上の積雪があった場合には雪下ろしが必要です。


落雪式
屋根の勾配を急にして雪を自然滑落させる構造の住宅です。落下した雪の堆雪スペースが必要で、近隣に迷惑をかけないように設計が必要です。

融雪式
屋根に融雪装置を設置し、融雪できる屋根構造の住宅です。融雪装置の燃料としては、ガス、灯油、電気などがあります。

克雪住宅補助・雪下ろし安全対策
市では「克雪すまいづくり支援事業」として、克雪住宅を建築する方や既存の住宅を克雪住宅に改良する方に対し、補助金を交付しています。
また、屋根の雪下ろし事故を未然に防ぐため、転落事故防止のための安全対策工事を行う方に対して費用の一部を補助しています。
冬仕度
車のタイヤ交換
道路が除雪されていても圧雪や凍結の恐れがあります。冬場のスノータイヤは必須で、車を運転する場合は降雪期前にタイヤ交換を行います。

雪囲い
雪下ろしを行うと1階部分の窓は雪でふさがれてしまいます。その際、窓ガラスが割れないように落とし板を十手金具(冬囲い金具)を使って設置します。また、庭木などの樹木を雪から保護するため、丸太や背板などで「雪囲い」を行います。
どちらも雪国では当たり前に見られる光景で、例年11月末頃までに作業を完了します。


雪国ならではの楽しみ
ウインタースポーツ
小千谷市はクロスカントリースキーやスキージャンプが盛んで、クロスカントリーコースやジャンプ台が整備されています。
小・中学校ではクロスカントリースキーの授業が行われるほか、市民が参加できるスキー大会なども開催されています。
また、里山が近くスノーシューなどを楽しめるほか、スキー場へのアクセスは車で30分と、様々なウィンタースポーツを楽しむことができます。



雪遊び・伝統行事
かまくらづくりや雪合戦、ソリなどの雪遊びは日常にあふれています。
また、1月には市内各地域で小正月行事の「さいの神」が雪上で行われ、焼いたするめや餅を食べて一年の無病息災を祈ります。さいの神は、豊作を願う「鳥追い」や雪灯篭、打ち上げ花火など、地域によって異なる風習も雪国暮らしの楽しみの一つです。




白銀世界
一面に広がる雪景色は雪国ならではの景観です。冬の貴重な晴れ間をめがけて多くのカメラマンが小千谷を訪れます。



春の訪れ
雪解け後の里山は山菜の宝庫、雪国暮らしの醍醐味の一つです。
※山菜採りは里山所有者や地元町内の許可が必要です。